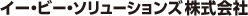対談・コンサル×ベンダーの挑戦:ナレッジDX化プロジェクトの舞台裏

対談・コンサル×ベンダーの挑戦:ナレッジDX化プロジェクトの舞台裏
2025.09.01
GE VERNOVA ソリューションアーキテクト 久冨 修平 氏
イー・ビー・ソリューションズ株式会社 ディレクター 高橋 宏知
イー・ビー・ソリューションズ株式会社 プリンシパルディレクター 五嶋 仁(コーディネーター)

左:EBSS 高橋 右:GE VERNOVA 久冨氏
当社では、多数のDX(デジタル・トランスフォーメーション)プロジェクトのマネジメント支援を手掛けております。本対談では、急速に進展するデジタル技術を活用した「ナレッジDX」プロジェクトの舞台裏と、その将来的な可能性について掘り下げていきます。
プロジェクトの背景
近年のテクノロジーの進展に伴い、クライアント企業では多機能かつ高性能な新たな生産設備の導入が進んでおりました。一方で、老朽化した設備も依然として稼働しており、それらに対応するためには、高度かつ幅広い設備保全の技術と知識が求められています。
これまでは、保全員の経験と熟練の技術によって、最適な設備保全と安定した生産が支えられてきました。しかし、ベテラン保全員の減少が進む中、ナレッジの継承と活用を図りながら、業務の属人化を抑えた新たな保全体制への転換が急務となっておりました。
対談(以下、敬称略)
五嶋: まず、お二人の出会いとプロジェクトでの役割について教えてください。
高橋:2020年頃、大手製造業のクライアント企業で「ナレッジDX」プラットフォーム構築プロジェクトが立ち上がったのが、私たちの出会いのきっかけです。私はクライアント企業側のプロジェクトマネージャーとして参画していました。
久冨:私はソリューションベンダー側のプロジェクトマネージャーとして、本プロジェクトに携わっていました。
五嶋:クライアント企業の期待値について教えてください。
高橋:大きく2つの期待がありました。
①グローバル展開を見据えた標準プラットフォームの構築
②クライアント企業自身が、プラットフォーム上で業務プリケーションを実装できること
久冨:以前は①のニーズが中心でしたが、ここ数年で状況が変わってきました。専門的なIT知識がなくてもアプリケーションを構築できるようになったことで、②の要望が増えてきています。

五嶋:プロジェクトで印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
久冨:DXでは大量のデータを扱うため、パフォーマンスの課題は避けて通れません。今回のプロジェクトでも、パフォーマンスに関する合意形成には時間を要しました。
高橋:ナレッジをデジタルで再現するには、細かな粒度のデータを保持する必要があります。一方で、リソースには限りがあるため、CPU・メモリ・ディスクなどのバランスを見極めながら処理ロジックを工夫して、最適な解を導き出すことが重要だと考えていました。約半年にわたる机上検討と実証を重ねた結果、最適解を導き出せたことは大きな成果だったと感じています。
五嶋:GE VERNOVA社に対する印象はいかがですか。
高橋:GE VERNOVAのDX製品群の充実ぶりには驚かされました。クライアント企業から寄せられた多くの要望に対して、標準機能で対応可能なケースが多く、対応が難しい場合でも、アドオン開発ではなく、標準機能として迅速に実装・リリースされるという手厚いサポート体制に感銘を受けました。
久冨:製品改良の観点から、クライアント企業の声は非常に貴重だと捉えています。アドオン開発による機能は、バージョンアップ時に取り残されるリスクがありますが、標準機能として取り込むことで、クライアント企業には継続的にSaaSサービスにおける継続的なバージョンアップのメリットを最大限、享受いただけると考えています。
五嶋:プロジェクトを進めるうえで工夫された点を教えてください。
高橋:蓄積されているナレッジには、大きく3つの種類がありました。
①すでにデジタル化されているもの
② 紙ベースで管理されているもの
③暗黙知として存在するもの
特に③の暗黙知については、処理ロジックを含めた形でデジタル化することに注力しました。その際、業務ユーザーも巻き込みながら、アジャイル手法を活用して短いサイクルで成果を検証し、精度の向上に努めました。クイックに結果を確認できることで、柔軟かつ効率的な対応が可能になったと感じています。

五嶋:最後にナレッジのDXの将来性についての考えを教えてください。
高橋:今回のプロジェクトを通じて、長年にわたり蓄積されてきたナレッジの継承と活用の有効性を改めて実感しました。一方で、AIをはじめとするテクノロジーが指数関数的に進化している中、それらに柔軟に追従していく姿勢もますます重要になってきています。少し大げさかもしれませんが、日本の製造業が再び世界で存在感を示すためには、“ナレッジのDX”が重要な鍵の一つになると考えています。
久冨:私も同感です。ソリューションベンダーとして、AIへの過度な依存に陥るリスクを慎重に見極めながら、企業が長年培ってきたナレッジを資産として活用できるような、より高い価値を提供できるソリューションの開発に取り組んでいきたいと考えています。
<商標注記>
文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
■協力: GE VERNOVA